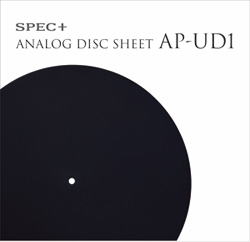ADプレーヤー
2020年11月22日補記
○ ビクター QL-F5 1980年 1979年発売 49800円

フルオートプレーヤー
クオーツロック・ダイレクトドライブ
WOW 0.025%
SN比 78db DIN‐B
消費電力 10.3W
重量 8.2kg
カートリッジ 付属 Z-1S MM
私の最初のプレーヤー。
特徴 オーディオの軌跡のページより
可変型オイルダンプアームを搭載したフルオートプレイヤー。
特殊な構造のためフルオート機では採用できなかったオイルダンプアームの問題点を独自の構造設計によって解決し、搭載しています。
回転系にはダブルサーボのクォーツロック回路を搭載しており、振動の少ないコアレスDCモーターとサーボ回路を一体化したMCコンバイン方式で信頼性を高めています。
リピート装置を搭載しています。
マニュアル操作優先設計が採用されています。
キャビネットには複合素材を採用しており、振動や共振の影響を低減しています。
なにやらありがたい言葉が並んでいますね。初めてのプレーヤーでしたので、何でもすごい!ということでしたが、すぐにダイレクトドライブのゴロ音が気になりだしました。要するにSNが悪いのです。
その後、長岡鉄男おすすめのトリオのKPシリーズにのめりこんでいくのでした。
○ KP‐800 1982年 売価 85000円
当時、長岡鉄男氏が勧めるハイコストパフォーマンス機として導入。
動作の仕方が、ビクターのフルオート機とは雲泥の差。大人と子供の差ほどあった気がします。

セミオート
クオーツロック・ダイレクトドライブ
WOW 0.006%
SN比 78db DIN‐B
重量 11.5kg
消費電力 18W
これに、A.テクニカのAT32Eをつけていた。
DLモーター。ダイナミックセンターロックシステムといって、センタースピンドルに溝が切ってあり、回転することによって、回転軸の中心に、セットされるという優れた機構を有していた。
音は、音場感が見事。音像は輪郭鮮明で小さく引き締まって定位もふらつきなし。
○ トリオ KP‐880D 1983年発売 89800円
これも長岡鉄男氏のダイナミックテスト評論を確認しながら導入したな〜。
ストレートアームは初めて。
コチコチの音になっていった気がします。

DCサーボ、DD、DLモーター
WOW 0.018%
SN比 65db
アーム スタティックバランス ストレートアーム(DSアーム)
音は、情報量が極めて多く超微粒子の感じ。音場、音像再生能力抜群。
○ ヤマハ GT‐2000X 1985年 1985年発売 320000円

本品は、その当時Nやからの出物で入手。専用付属のスタビライザーが欠品していたもの。
憧れのGTシリーズのプレーヤーを入手できるのはこれが最後と、就職したばかりの私が頑張って入手した物でした。
外部電源付きでした。
当時のアクセサリーで、砲金製ターンテーブル。真鍮削り出しアンカーブロック。ストレートアーム、などがありましたが、当時はとても手がです。
ヤマハGTシリーズの頂点。
DCサーボ、DD。
重量 34kg
WOW 0.0025%
SN比 85db
消費電力 12W
外部電源使用
アウターパワーサプライYOP-1。
YOP-1はGTプレイヤーに内蔵された電源の約2.5倍の容量を持った専用外部定電圧電源ユニットで、強力電源によって回転系の安定性を高めるとともに、ストップ時の電子ブレーキとしても利用できます。
オーディオの足跡から
解説
GTシリーズの頂点モデルとして発表されたレコードプレイヤー。
モーターには、起動トルクを稼ぐよりも実演奏時のリップルノイズの影響を配慮した新開発DC4相8極コアレスホールモーターを採用しています。また、モーターシャフトには直径20mm、長さ60mmの世界最大級の精密シャフトを採用しています。
ターンテーブルには、鍛造アルミ切削仕上げによる374mmφ・5.8kg・慣性質量1.2t/cm2(マット含む)の精密ターンテーブルを採用しています。
トーンアームにはジンバルサポート方式ストレートアームのYSA-1を標準装備しています。
このアームでは信号経路から磁性体要素を排除するため、アーム素材やピンジャックなどに黄銅を採用しています。また、ヘッドシェルには非磁性・アルミ切削のものを採用しています。
さらに、1.2mmφのOFCリード線やITK#3000の使用により、信号往復抵抗0.15Ωを実現しています。
GT-2000XにはGT-2000でオプションだったオートリフタYAL-1を標準装備しています。
YAL-1は非接触光学式で滑らかな動作と優れた操作性を実現しています。
ディスクスタビライザとして、74mmφx34mmのアルミ真鍮複合型ディスクスタビライザのYDS-8を標準装備しています。
キャビネットには高密度パーティクルボードを用いた積層型となっており、底板を含めて6層155mmの厚さとなっています。
このキャビネットだけで19kgの重量があり、しかも積層にあたってはヤマハの木工技術を生かして接着剤の選別まで行い、十分に吟味された構造と形状を採用しています。
また、仕上げはアメリカンウォルナットをリアルウッドで用い、ピアノと々ポリエステル塗装で鏡面仕上げしています。
●ディスクスタビライザYDS-1が使用できます。
YDS-1は黄銅削り出しの盤を用いた電動ポンプ式レコード吸着システムで、原理的にレコード重量が4.5kgまで増加したのと等価の威力を発揮できます。
これは、一度セットしましたが、スタビライザ本体のこつこつ音が乗るのと、吸着用のゴム外周部がヘタるので、吸着が上手くいかなくなる、などの不具合で早々に外しました。
〇ステンレスターンテーブル
砲金製ターンテーブルが、法外な金額での取引になってしまったので入手をあきらめていたところ、北海道の業者がステンレス製のTTをヤフオクに出品しました。
18キロ18万円(だったか?)
純正のレコード盤保持用の半円状の溝がない平板タイプのTTです。
何しろ重い!
これはすごい効果をもたらしました。
なじむのに3年はかかります。
〇ターンテーブルシート
SPEC AP-UD1 2020年1月導入 定価24800円
これまでは、パイオニアのJP701を使っていましたが、SNが良くなる代わりにダンプが効いたおとなしい、悪く言えば、死んだ音だったのでした。
このAP-UD1に替えると、音が生き生きとして、楽しめる音に変身しました。
効能書きを読むとなるほどと思います。
SPEC社の社員は、パイオニアからでた人たちで、2020年パイオニア本体が滅亡状態にある中、SPEC社は元気(でいるよう)です。 (^^)
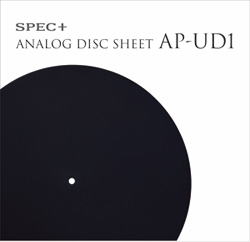
以下SPEC社の説明
スペックはアナログ・ターンテーブルGMP-70の開発にあたって、アナログ・ディスク・シートに関しても最上の音質を追究し、同時開発してきました。
これまでのアナログ・ディスク・シートは、柔らかい素材、たとえばゴムや皮が使われることが多く、振動を吸収する役割を担っていましたが、オーバーダンプになりすぎて音楽が死んでしまう危険性がありました。一方で硬い金属やガラスを使用すると、素材特有の振動が癖のある音を作ってしまいました。
ところでレコードを製作する最初の工程は、ラッカー盤に音楽を刻み込むカッティングです。レコードの溝をトレースするよりも強い力を要するカッティングにおいて、固有の癖を持たないで正確に信号を記録できるのは何故なのか?ラッカー盤を構成する薄いアルミ板とラッカーとの組み合わせが音源を忠実にトレースする最適の振動バランスなのではないか?
この仮説に基づき、アナログ・ディスク・シートAP-UD1では薄いアルミ板に特殊な表面処理を施しました。レコードのカッティングの際に近い状態のベストバランスを再現したのです。
APー70
サブシステム用に2020年導入

AP-70
62,000円(税抜)