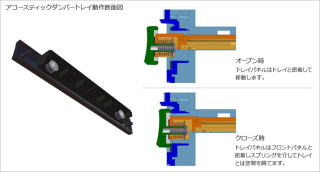HIVI 2015年1月号から 歴代パイオニアのプレーヤー
 左から LD-S1(1981年) LD-X1(1989年) HLD-1000( 1993年)
左から LD-S1(1981年) LD-X1(1989年) HLD-1000( 1993年)  HLD-X0(1995年) HLD-X9(1996年) DV-S9(1997年) DV-AX10(1998年) DV-AX5AVi(2005年) 一番右 BDP-LX91(2008年12月)
HLD-X0(1995年) HLD-X9(1996年) DV-S9(1997年) DV-AX10(1998年) DV-AX5AVi(2005年) 一番右 BDP-LX91(2008年12月)私は、ほぼリアルタイムで全製品のリリースに触れてきました。ハイビジョンLDプレーヤーはP社の迷走期のもの。すでにDVDメディアが主流になりそうな時期に、30センチ盤でハイビジョン(それもアナログ)を求めていたモノ。
LDS1、LDX1は画質がすごく良く、X1の黒の出方はこれまで見たことがなかったものでした。
1996年にDVD規格のソフトが発売され始め、WIKIによると5.1chサラウンドは、インデペンデンスデイ(1999年)から始まったようだ。当AVルームでは、1996年発売インデペンデンスデイは、LDでのサラウンド視聴だった。1996年当時はLD、DVD併売は当たり前で、一部LDの方が高画質だという論理もまかり通っていた。長岡氏くらいがまともに画質比較をしていた時代だった。
この写真にはないが、パイオニアは、LD規格の創始者で、LD1000(1981年)から始まるLDプレーヤーを世に送り出し、CDが1982年頃から登場すると、LD、CDコンパチプレーヤーCLD9000(1984年) を出した。CLD9000を、私は使っていました。
LD-S9(1996年)という傑作機もあった。これをコンパチにしたCLD-HF9Gという機種も私は使っていました。
DVD-S9は当AVルームにあった傑作機。
その後のパイオニア機は、747などの3ナンバー機種=軽薄短小になり、画質は向上したが、音はいまいち、という状態がBDP-LX91が出るまで続いてしまったのです。
同じくHIVI誌1月号から、パイオニアの技術者。右端が、平塚氏。

平塚氏は2年前、会津坂下のIKシアターに、評論家亀山氏とともに来ていました。
2年前は、SC-LX85のフルバンドフェイズコントロールと、AVプリ裏モード(パワーアンプをオフにしちゃう)での、音の良さを強調。ソニーのVW1000(ネイティブ4Kプロジェクター)のデモ、プレーヤーはパナソニックのBZT3000だったはず。
その時に私も同席し、平塚氏に、自分がBDP-LX91のユーザーであり、最近ファームウエアの更新が止まっているが、パイオニアでは、フラッグシップ機の扱いをどう考えているのか、と尋ねました。特にその当時3Dが流行っており、LX91での3D対応の可能性も尋ねたのでした。
実は、その当時パイオニアは事業見直しを進めており、AV、オーディオ、カーステレオ、他の事業の整理統合(2009年2月PDP事業撤退)を進め、本社を川崎に移転(2009年11月)するなど経営改善を図っていました。
平塚氏は、S9や、AX10を作り、LX91開発にも参加したのですが、その後、AVアンプ部門に移ってしまったので、その後のケアができなかった、という答えでした。パイオニアとしては、LX91はフラッグシップ機ではあるが、ファームウエアアップデート(更新)は終了。3D対応もできない。車で言うとエンジンが違うので不可能だ、と言われました。
パイオニア‐オンキョウになる、という事業統合の話が進む中、再び、パイオニアとして、BDの最高画質機を作る、という機運がようやく盛り上がり、2014年7月頃の新製品発表にこぎつけました。
実際、私自身の目で見るまで、この製品のすごさはわかりませんでした。
パイオニアのBDプレーヤーは、発売当初は読み込みが非常に遅く、同時期のソニーPS3と比較して全くお話にならない遅さでした。
ただ、これまで、S9やAX10を作ったパイオニアとしては、BDでも最高の物を、という気持ちがあったのでしょう、LX91 では、まあまあ気にならない程度まで出画時間が短くはなったのですが、それでもPS3やパナソニックのBDレコーダーからすれば遅かったものです。
今回のLX88はこの点は及第点をあげても良い位には早くなっています。



ブラックマスク。14.2kg。 8h分のDACを2chに使うというおごった設計の音声出力。 裏面。オーソドックスに4本足。(LX91は3本)
 黒パネルなので、ボタン類が判りにくいという事はある。デザイン優先か。
黒パネルなので、ボタン類が判りにくいという事はある。デザイン優先か。これが、暗闇のシアター使いにすると、使いづらいのだ。リモコンも自照式ボタンではあるけど、小さいボタンは懐中電灯を使わないと確認できないから最悪。パワーボタンの丸いイルミネーションがディマー設定でも暗くなってくれなくてまぶしい。ディマー消灯にすると、真っ暗になっちゃうのだ。(消灯を示す青いLED一か所はある。)