
青いのはブルージャイアントのサントラLP。
最新録音のジャズも楽しい。
○20241101 GT2000X 最近の撮影

青いのはブルージャイアントのサントラLP。
最新録音のジャズも楽しい。
〇202001 ターンテーブルシート交換
SPEC AP-UD1 26800円くらい

平滑なアルミ円盤にラッカーを塗布したシート。
アナログ盤を作成する行程で、リニアトラッキングの特殊な針を使ってラッカーマスターを作る。その工程に似せたシートをSPECが作った。
ブチル系のゴムシートは振動を吸収するが、音も殺してしまう悪影響が大きいとSPECは言う。
試聴会で、SPEC AP-70 で交換して実際に聴いたのでその効果は折り紙付き。

パイオニアJP701のブチルで抑えられていた音楽が、にわかにはじけだして何とも楽しい音が飛び出してくる。
ずーっと、パイオニアのJP501、JP701 を使い続けてきたが、今になってハード系のシートがはまってしまった。
というのも、ターンテーブルが鳴きが皆無の既述重量級TTに変わっていたから。
これがぽこぽこのターンテーブルだとダンピングが必要になってきます。
○20151010 ターンテーブル交換
北海道小樽の事業者氏から購入。ステンレスSUS304無垢材を切削加工、18.8kgの超重量級TT。
GT2000用と記載されているが、2000xもセンタースピンドル形状は共通。純正オプションYGT-1は、両機共通でした。
今回は、砲金製YGT-1がとても手に入らない環境になってきたこと。ヤフオクで、この出品者が10年以上前からステンレスTTを自作、GT2000
系に装着、実働。この4か月でも5枚以上販売実績を持っていることなどから導入を即決。
北海道から蟹ならぬ、ステンレスの塊が届きました。


室温に慣らしてから装着。 定番JP701(501の後継機種だったが実は、これも廃版だった、、、)


オリジナルにあったU字溝はない。 平面のターンテーブルは、英式のプラッターという名にふさわしい。
重量が3倍以上増え、起動・安定回転に達するまで若干時間がかかります。いったん回ってしまえば、盤面クリーナーなどを押し当てても止まってしまうことはありません。
逆に、外部電源効果で、停止時は、オリジナル時に変わらない時間で停止します。


アームの高さ調整はとりあえずしていない。 純正とサイズ、高さなどが共通なのだ。
演奏実際は、スタビライザーを真鍮製、大重量の物で行った。
起動、停止の確認のために、このテクニカのスタビを使用。


オリジナルTT。いったん18キロを持ってしまうと、5キロほどのこれが軽く感じてしまう。
片付けたら、オリジナルの茶色いターンテーブルシートも出てきたので、併せて保管する。
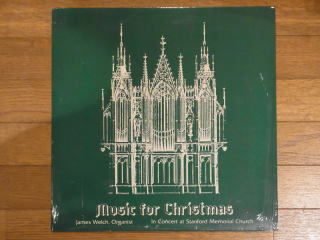
チェックディスク。長岡鉄男氏超A級外盤セレクションの一枚。パイプオルガンの地をゆさぶる地鳴りに似た低音が再生できました。
これはすごい。これまでは、超低域が、鳴っているな〜と感じるくらい。ホールで直に聴いた時のあの揺さぶられ感が出てくると、かなり驚きます。
実は、プレーヤーラックも、タオックの重量ラックに変更していたのでした。これまでのクワドラスパイアのラックではちょっと何でした。
こうなると、深夜ではなく通常の時間帯に、どっかん、とやってみたくなります。
ポップス女性ボーカルものも、低域がしっかりすることによる、中高域伸張効果で、しっとりと歌い上げる再生が楽しめます。
レンジとしては80年代ポップス音作りの八神純子。このシステムで聴くと、80年代に戻ったような瑞々しいボーカルが聴けます。
装着直後で、ターンテーブルシート、TT本体、スピンドル、GT2000X筐体、アーム、カートリッジ、などなどとの親和が進めば、さらに良くなる感じの印象です。エージングでどのように変わっていくかが、楽しみです。
○20131110 カートリッジ変更
 クアドラのラック天面に突出しているねじ山にGT2000Xの脚が当たるのでななめにずらして設置。
クアドラのラック天面に突出しているねじ山にGT2000Xの脚が当たるのでななめにずらして設置。

 このメカメカしさがたまらない。
このメカメカしさがたまらない。

 スタイラスクリーナーSC2は空になってしまった。
スタイラスクリーナーSC2は空になってしまった。


 一時こんなに重くてスピンドルに負荷かかりすぎじゃないか、と思ったが、砲金製ターンテーブルはこれよりかなり重いので問題なし。
一時こんなに重くてスピンドルに負荷かかりすぎじゃないか、と思ったが、砲金製ターンテーブルはこれよりかなり重いので問題なし。
 完動品で感動。
完動品で感動。 アームは純正ストレートアーム。どこかのツワモノは、このパイプの中に走っているコード(細より線)を外に出し、カスタマイズしている人もいます。確かに、パイプ内のコードは、アームジンバル部で、余計な力をアームに加えています。
アームは純正ストレートアーム。どこかのツワモノは、このパイプの中に走っているコード(細より線)を外に出し、カスタマイズしている人もいます。確かに、パイプ内のコードは、アームジンバル部で、余計な力をアームに加えています。
