DVDプレーヤー、LDプレーヤー、CDプレーヤー
○ ソニー DVP‐S7000
PS3でDVD再生を試みていたが、ついにDVDプレーヤーを導入しました。
DVP-S7000 1997年発売
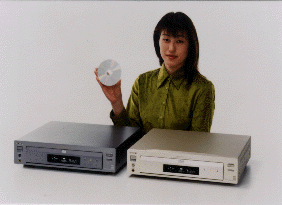
家のは、ゴールドの方。
ソニーDVDプレーヤーの初代機。フロントパネルの開き方が独特。またでかいリモコンは結構使いづらかった。
パイオニアのS9に精細感で負け代替となったが、力強い画は好きだった。
ソニーの解説より
ソニーは、DVDビデオソフトの高画質映像を再現するDVDプレーヤー『DVP-S7000』を商品化し、3月より発売します。本機は、当社がCDをはじめとするデジタル機器の開発・商品化で培ってきた光学系、半導体、画像圧縮技術により、DVDビデオソフトの高画質な映像、高音質な音声をお楽しみいただけます。DVDビデオソフトの他、音楽CD、ビデオCD(Ver.2.0)の再生も可能です。
| 型名 |
発売日 |
価格(税別) |
本体カラー |
当初月産 |
CD/ビデオCD/DVDプレーヤー
『DVP-S7000』
リモコン『RMT-D101J』付属 |
1997年3月21日 |
110,000円 |
ゴールド
チタニウムグレー |
5,000台 |
DVDはCDと同じ直径12cmの光ディスクに4.7GBの大容量データを収録することができ(片面一層ディスクの場合)、画像圧縮技術として MPEG2
規格を使うことで、水平解像度約500本の高画質映像を約133分*1記録することができます。映像再生としてのDVD-Video、コンピューター分野のDVD-ROMや、DVD-R*2、DVD-RAM*2、音楽分野のDVD-Audio*2など様々な用途での利用が考えられます。また21世紀のマルチメディア時代*3に向けて、コンピューター用データストレージやカーナビゲーションシステム、ゲームプレーヤー等幅広い応用が期待されています。
今回発売するDVDプレーヤー『DVP-S7000』は、当社が独自に開発した“独立デュアルピックアップ”を搭載、CD再生、DVD再生各々に専用ピックアップを用いることにより、異なる物理特性を持つ各ディスクに対し、最適な信号の読み取りが可能です。また
ディスクの反りや回転時の傾きを電気的に検出し、光軸を常にディスクに対して垂直に保つ“チルトサーボ機構”を採用し、安定した映像の再生を実現しています。さらに“デジタルRFプロセッシングLSI”を搭載し、ディスクごとにジッター値をデジタル計測し、ピックアップのフォーカスや“チルトサーボ機構”等を電気的に制御することにより、エラーレートの極めて低い読み取りを実現しています。
画像処理に関しては、DVDディスクからの8ビットのデータを10ビットに変換し、演算処理を行なう“映像D/Aコンバーター”を採用し、映像情報の細部までを忠実に再現いたします。音声は、当社
高級オーディオにも搭載されている“フル・フィードフォワード方式デジタルフィルター”や“カレント・パルスD/Aコンバーター”を採用することにより、高音質再生を実現しています。
さらに当社独自の“スムーズIPサーチ”を実現。自社開発のMPEG VideoデコーダーLSIを高速32ビットRISCチップマイクロプロセッサーで制御することにより、圧縮フォーマットでありながら、正逆方向への動きのなめらかなスロー・コマ送り等多彩な変速再生をお楽しみいただけます。
本機はホームシアターユーザーの視聴スタイルを追求した“テーブルトップリモコン”を装備、“クリックジョグシャトル”等を搭載し、変速再生時の操作性を考慮した設計を図っています。
○ パイオニア DV-S9
1997年12月発売

物量投入型シャーシを使用。銅メッキシャーシ、大型電源などよき時代のパイオニア製。
パイオニアのサイトから
解説
| 商品名 |
型番 |
価格(税別) |
発売時期 |
月産予定台数 |
| DVDプレーヤー |
DV−S9 |
190,000円 |
12月中旬 |
1,000台 |
【企画意図】
DVDが国内市場に登場して1年が経つ現在、DVDビデオソフトのタイトル数は500を超える勢いで増加しており、DVDビデオプレーヤー市場も活性化が進んでおります。
当社はこれまでに、DVDビデオプレーヤー3機種、DVDカラオケプレーヤー2機種、計5機種の業界最多ラインナップを発売し、好評を頂いております。中でもDVDとLDのコンパチブル再生を可能にした「DVL−9」は、機能性の高さ、コストパフォーマンスの良さも相まって高い評価をいただき、トップシェアの地位を築いております。
一方、現在のDVD購買層の中心であるマニア層からは、より高性能なモデルの発売を望む声が多く聞かれ、当社ではそのニーズに応えるために「DV−S9」の開発、製品化に取り組んでまいりました。
「DV−S9」には、当社がこれまでに培ってきた光ディスク技術とオーディオ技術が集大成されています。画質においてはコンポーネントフレームDNR
ICをはじめとする新開発LSIを搭載するなど、ソフト制作者の意図した映像により忠実な再現を実現。音質においては当社の高級CDプレーヤーと同様の設計思想により、96kHz24bitマルチビットオーディオDAC、Hi-bit・レガート・リンク・コンバージョンS機能などを搭載して高音質化を図り、フラッグシップモデルに相応しいハイクオリティを実現いたしました。
○ パイオニア DV‐S747A 2001年9月~2004年2月 2001年発売99800円

S9より画質が良いということで導入したが、音はいまいち。最後まで音が悪いので一線に残れなかった機械。画質はD‐1をしのぐ部分もあったが、969aviのhdmi接続は747もd‐1も凌駕した。結局、969導入は見送られUx‐1が来たのは、物量投入型シャーシ、物量投入型メカによる音のよさが決めてだった。
パイオニアのサイトから
解説
| DVDオーディオ/ビデオプレーヤー |
DV-S747A |
99,800円 |
11月下旬 |
2,000台 |
【企画意図】
DVDプレーヤーの市場は、現在本格的な普及期に入り、2001年の国内販売台数は120万台に達するものと見込まれます(JEITA予測)。またDVDビデオソフトは、15,000タイトル(パイオニア調べ)を超え、さらにDVDオーディオソフトも年内に約100タイトルが出揃うと予測(パイオニア調べ)されていることから、今後DVDビデオ、DVDオーディオ両方の再生が可能なユニバーサルプレーヤーへのニーズが高まっております。
この度発売いたします2機種は、DVDオーディオ/ビデオプレーヤーとしては業界初のスーパーオーディオCDマルチチャンネルにも対応しながら、10万円を切る価格を実現した「DV-S747A」と、プログレッシブスキャンを搭載したお求めやすい価格の「DV-S646A」です。当社は、今回発売する2機種の追加により、さらなるラインアップの強化をはかり、DVDのリーディングカンパニーとして、お客様の様々なニーズにお応えしてまいります。
【「DV-S747A」の主な特長】
1 ) スーパーオーディオCDマルチチャンネル再生
DVDオーディオ/ビデオ再生に加え、スーパーオーディオCDのマルチチャンネルディスク再生を実現しました。
2 ) 高画質12bit/108MHz映像DAC搭載*
業界の最高水準である最新の12bit/108MHz映像DACを搭載*。オーバーサンプリング処理によって、従来のD/A(デジタル/アナログ)処理で生じていた信号の劣化や、折り返しノイズを大幅に抑制し、映像のレベルを高めております。
○ エアー D‐1
画像は、2020年の頂き物。
当時我が家にあったのは、黒。
マルチチャンネル出力付きのタイプでした。


プログレッシブ回路搭載のD-1。音像の輪郭。深深とした音場。
映像は、質感があり、奥行き感も出る。
EAD シアターマスターシグネチャーとの組み合わせで、高レベルの再生音を実現。
ボーカルの実体感、肉感的表現はすばらしい。
またDVD映画再生についても、非常に良好な再生音場を作り出す。
 当時の画像
当時の画像
サイズが小さいです。
○ エソテリック UX‐1
物量投入型シャーシ、メカ、電源、基板など。パイオニアがAX10やS9クラスのシャーシでS969aviを作ったら、悩む人はたくさんいただろうに。軽いプレーヤーは音が悪い。パイオニアにDVDプレーヤーは画質は良い。しかし、CD、SACD、DVDなどどれを聞いても音は悪かったのだ。
UX-1は、映像ダックの性能が969と同等。メカははるかに凌駕しているので、DAC性能以上の画質差になっている。
LDプレーヤー
○ パイオニア CLD-9000 1985年 1984年発売 249800円

CD、LDコンパチプレーヤー
当時、CDプレーヤーを持っていなかったので、CD-LDコンパチ機を選択。
重量 16kg
消費電力
メカは強靭なダイカストフレームにCDメカと別のLDメカを90度に取り付け、電源もモーターも強力。音もそれにふさわしいもの。CDは、輪郭鮮明、ダイナミックでエネルギッシュ。多少きめの粗さはあるが、スケールが大きいので良しとする。
パイオニアのサイトの説明
1984年に発売された世界初のLD/CDコンパチブルプレーヤー。当時普及し始めたCDとの互換性を持つ本モデルの発売により、新しいメディアとの互換性をプレーヤー側で確保する考え方が業界で定着し、その後のDVD、ブルーレイディスク(BD)においても継承されました。
○ パイオニア CLD‐110 1990年 発売1990年 69800円

これも長岡鉄男氏の評価を見て、まあまあの物だったので導入。
コンパチ機である。
重量 7.6kg
消費電力 32W
F特 4から20Khz ±0.5db
DIST 0.0022% EIAJ
DACはマルチビットではなく1ビットタイプに変わった。画質は、きめが細かい。解像度が特に上がったわけではない。シルキータッチのアナログ的画面。ただ、その分画に力がない。音も同様にシルキータッチだが、エネルギー感はいまいち。
○ ケンウッド LVD‐Z1
1992年発売、当時250000円

突然変異的に、ケンウッドから登場したLD;プレーヤー。
デザイン、重量、動作、画質とも、パイオニア、ソニーに負けず劣らず高性能機でした。
長岡鉄男氏が絶賛したので、導入。そのころ氏は、ソニーの超重量LDプレーヤー(MDP-911?1988年22万円18キロ)を絶賛使用していたのですが、瞬間的に箱舟で使われたと思います。
幅が若干大きく、ラックの内側をカンナ掛けして収めました。
力強い画質。CLD110とは性格が反対の傾向で素晴らしかった。
3次元Y/C分離LSI搭載、デュアルDAC7音声回路搭載で、画質だけでなく音質も良かった。
○ パイオニア CLD‐HF9G
ネットからの拾い物です。
我が家にあったのも、これと同じシャンパンゴールドのもの。
最後は、読み込みに若干難があったものの動作品で、ペアのAVアンプともに活躍していました。

LVDZ1に対して精細感が上回った。力強さより精細感を重視した。でもLVDZ1の物量投入型シャーシ。高級感あふれるデザインは捨てがたいなあ。この時期のケンウッドは特異的にデザインが良かったのだ。
CLD-HF9Gはその後も、現役を続けていたが、画質はDVD、ハイビジョンを見てしまうと、ファーマットの差は隠しようが無く、一般の試聴に耐えられなくなってしまった。
以前は、高画質で喜んでいたのにね。
たくさん買った「高画質盤」「CAV盤」「プレミアムエディション」「限定盤」数々のLDコレクションはどうしよう???
2015年ころまでに、LDは全部売り払い処分しました。
本機も、LDをDVD化した後、動作状態のうちに売却しました。
CDプレーヤー
○ ヤマハ CDX‐2200 1987 1987年発売 168000円

18ビット4倍オーバーサンプリング、デジタルボリューム搭載。
重量 15kg
消費電力 25W
非常にナチュラルな音だった。
18ビットDACがその要因だったようだ。
(標準は16ビット)
B級オーディオFAN様のサイトからの引用
YAMAHA製の、18bit・4倍オーバーサンプリングのデジタルフィルターと、バーブラウンの「PCM56P」をフローティング動作させた、YAMAHA仕様の18bitDACです。
バーブラウン PCM56Pは、多くのメーカーで採用された優秀なDACで、CDX-2200では最高グレードのKタイプを、左右独立で搭載しています。
YAMAHA CDX-2200のスペック
| 周波数特性 |
DC~20kHz±0.3dB |
| ディエンファシス偏差 |
±0.3dB |
| 高調波歪率 |
0.002%以下 |
| ダイナミックレンジ |
100dB |
| S/N比 |
115dB |
チャンネル
セパレーション |
100dB以上 |
| 消費電力 |
25W |
| サイズ |
幅435×高さ125×奥行400mm |
| 重量 |
15.0kg |
○ ナカミチ CDP‐2
1990年発売 99800円

チェンジャー機構が秀逸。音は広広とした音場。おとなしい表現。ドスンバリバリといった表現は出来ない。
1.jpg)
CDPのメカ。
これが曲者だった。
右サイドのローディングベルトと、メカ全面の角ベルトが3年でスリップするようになり、スリップするとディスクを入れ替え、チャッキングすることが出来なくなる。そのせいで、ピックアップやDAC、電源などが無事でも動作不良でNGとなる機種であった。
これは、1000mbも基本同じメカ。
業務用のもの、車載用のもの、それと、NF工場閉鎖後のMBメカは、その辺が改善されて信頼性は向上したが、ときすでに遅く。
○ ナカミチ 1000mb
1991年発売 55万円
 DAC付きのmb/iもあった。
DAC付きのmb/iもあった。
1000Pとの組み合わせで広大な音場。整然と並ぶ音像には、すぐれたものがある。しかし、音像が並んで聞こえるということは深深とした音場表現が出来ていないことの裏返しなのであった。
銀のようなしゃらららン、となる鳴り方ははまる人にははまるのであろう。
物量投入型シャーシ、電源、基板であったが、メカが汎用品だった為、いまいちブレイクするところまでいたらなかったのが惜しい。
考え方は面白いのだが。音圧、光をシャットアウトする構造は、ナカミチでしか出来なかったもの。それが音にもっと結びついていればなあ。
MBメカ自体にメンテが必ず必要な部分があり、高価格品の割には信頼性が劣ったのも売れなかった要因か。
○ linn LT2 ベルトドライブのCDプレーヤー 2003年ころ
音はいまいち。おやぢのシステムには合わなかった。
2020年11月、画像を探したが見つからず。自分もこのコンポのことを全く覚えていない。残念。

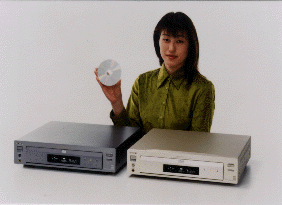




 当時の画像
当時の画像




1.jpg)
 DAC付きのmb/iもあった。
DAC付きのmb/iもあった。